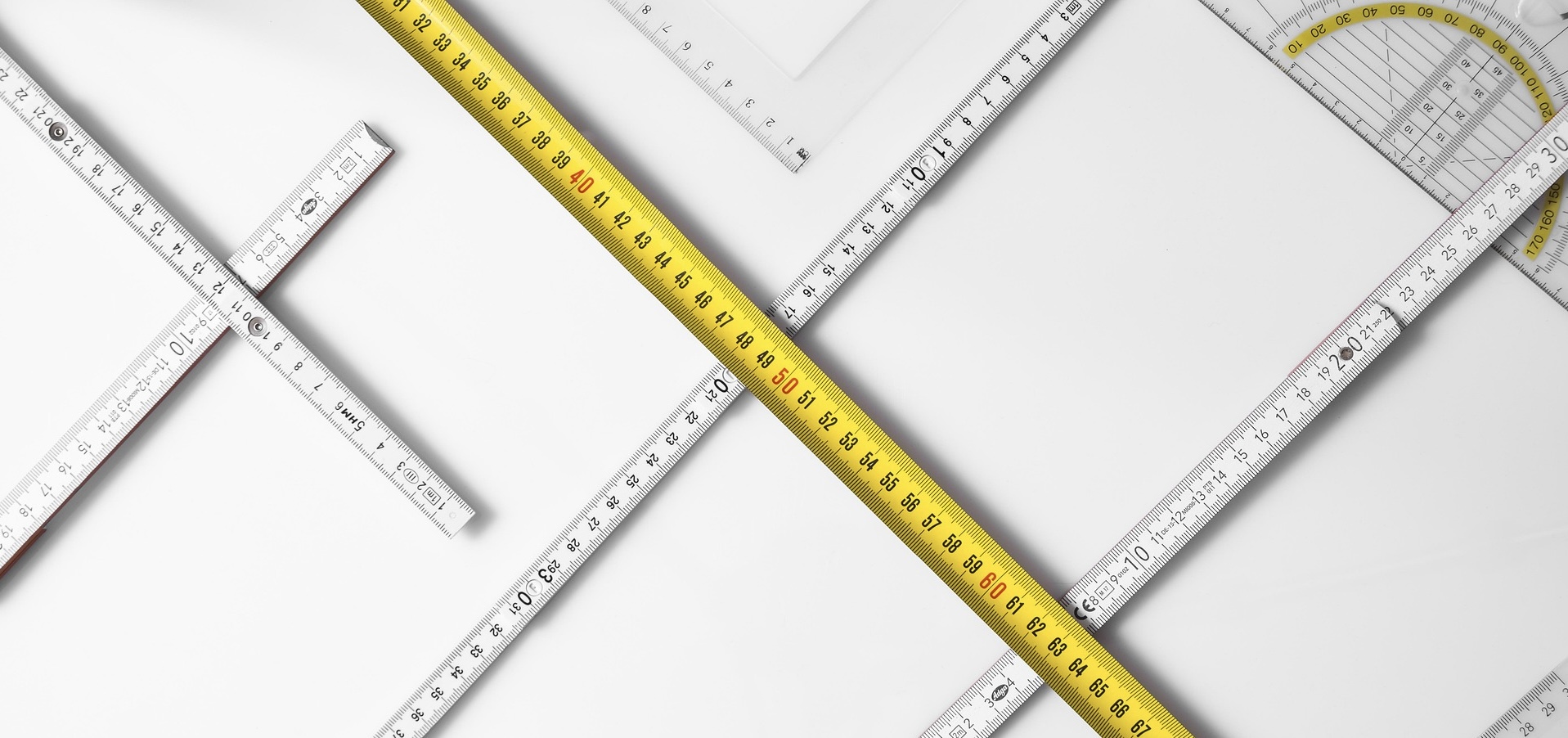
このページでは国内外の絵画の基準寸法、紙の寸法などについて記述し、日本における額縁の規格サイズの由来を解説しています。額縁の規格サイズをお調べの方は、ここをクリックして一覧表をご覧ください。
額縁の規格サイズとは、どのように規格として決められたのでしょうか。
額縁の規格寸法は、絵画等に使われる紙やキャンバス等の基底材の標準寸法、または、額縁を構成する素材の採り分等の要因から決められてきました。
ここでは国内外の絵画の基準寸法、紙の寸法などについて記述し、日本における額縁の規格サイズの由来に迫りたいと思います。
現在世界中で使用されている額縁の寸法は、大別するとメートル法(フランスの寸法)を使用している欧州と、 インチ(アメリカの寸法)を使用している米国やカナダなどの2系列に分けられます。
今日のようなキャンバスの木枠が使われだしたのは、19世紀末頃からといわれています。 それ以前のフランスやイギリスでは、現在使われているFサイズ(人物画用)に似た規格寸法らしきものもありましたが、一部での利用に限られていたようです。
規格サイズが浸透するまでは、作家が適当な大きさの布(キャンバス)に気ままに絵を描き、完成後に作品の大きさに合わせて木枠と額縁を作るのが一般的でした。
フランスの寸法はメートル法を採用している国々で使用されています。
人物・風景・海景を描くのに最もふさわしいとされている3つのサイズを基準とし、F(Figure/人物)・P(Paysage/風景)・M(Marine/海景)と呼んでいます。
近年規格サイズとして一般化したS(Squer/正方形)があり、個々の大きさの名称は号数をつけて呼称されます。(例:F6号、P6号、M6号、S6号) それぞれの縦・横の比率は、Fにおいては(√5-1):1、Pでは√2:1、Mでは(√5+1):1の近似値となっています。Sはいうまでもなく1:1となります。
その基本は古代ギリシャ時代から伝わっている、最も美しい形といわれる黄金率より算出されており、その対比は二辺の長さをそれぞれa,b(a<b)とするとき、a:b=b:(a+b)となるような比を持つ長方形がそれにあたり、Mの形がちょうどそれに該当します。
また、FはMの長辺同士を並べるとFの比率に等しくなり、これも黄金率に該当します。Pは正方形の一辺と、その対角線を組み合わせたもので、その比率はFとMの中間に位置しますが、黄金率とは独立したものです。しかし、これらのフランスの寸法は従来の黄金率を基本としているものの、F・P・Mの三種類の規格における各辺同士の互換性を考慮した寸法が現在使用されているために、本来の比率と誤差が生じています。
※黄金率/Golden Section…線分を二つに分割するとき、長い部分と短い部分の比が、全体と長い部分の比に等しくなるような比。黄金率には美観と調和があり、古代ギリシャ時代より美術や建築などで用いられています。
フランスのキャンバス寸法表(単位:cm)
|
号数 |
Fサイズ Figure |
Pサイズ Paysage |
Mサイズ Marine |
|---|---|---|---|
|
0号 |
18×14 |
18×12 |
18×10 |
|
1号 |
22×16 |
22×14 |
22×12 |
|
2号 |
24×19 |
24×16 |
24×14 |
|
3号 |
27×22 |
27×19 |
27×16 |
|
4号 |
33×24 |
33×22 |
33×19 |
|
5号 |
35×27 |
35×24 |
35×22 |
|
6号 |
41×33 |
41×27 |
41×24 |
|
8号 |
46×38 |
46×33 |
46×27 |
|
10号 |
55×46 |
55×38 |
55×33 |
|
12号 |
61×50 |
61×46 |
61×38 |
|
15号 |
65×54 |
65×50 |
65×46 |
|
20号 |
73×60 |
73×54 |
73×50 |
|
25号 |
81×65 |
81×60 |
81×54 |
|
30号 |
92×73 |
92×65 |
92×60 |
|
40号 |
100×81 |
100×73 |
100×65 |
|
50号 |
116×89 |
116×81 |
116×73 |
|
60号 |
130×97 |
130×89 |
130×81 |
|
80号 |
146×114 |
146×97 |
146×89 |
|
100号 |
162×130 |
162×114 |
162×97 |
|
120号 |
195×130 |
195×114 |
195×97 |
アメリカの寸法はインチ寸法を採用している国々で使用されています。
アメリカの寸法は至極合理的で、ほぼ2インチ(inch)刻みで規格寸法ができており、 個々の大きさの名称は、縦横各一辺の延寸法(UNITED INCHES)、たとえば、8×10インチの場合、 ”UNITED INCHES 18”で表示されています。一般的には8×10インチの場合エイト・バイ・テンのように寸法で呼ぶことが多いようです。
アメリカのキャンバス寸法表(単位:インチ)
※1インチ=2.54㎝
|
UNITED INCHES |
インチ(ミリ) |
UNITED INCHES |
インチ(ミリ) |
|---|---|---|---|
|
○ 12 |
5×7 (127×177.8) |
○ 16 |
7×9 (117.8×228.6) |
|
○ 18 |
8×10 (203.2×254) |
○ 20 |
9×11 (228.6×279.4) |
|
22 |
10×12 (254×304.8) |
○ 25 |
11×14 (279.4×355.6) |
|
27 |
12×15 (304.8×381) |
○ 28 |
12×16 (304.8×406.4) |
|
32 |
14×16 (355.6×406.4) |
○ 34 |
16×18 (406.4×457.2) |
|
○ 36 |
16×20 (406.4×508) |
38 |
17×21 (431.8×533.4) |
|
○ 40 |
18×22 (457.2×558.8) |
42 |
20×22 (508×558.8) |
|
○ 44 |
20×24 (508×609.6) |
46 |
20×26 (508×660.4) |
|
48 |
22×26 (558.8×660.4) |
50 |
22×28 (558.8×711.2) |
|
52 |
24×28 (609.6×711.2) |
○ 54 |
24×30 (609.6×762) |
|
55 |
25×30 (635×762) |
56 |
24×32 (609.6×812.8) |
|
58 |
26×32 (660.4×812.8) |
○ 60 |
24×36 (609.6×914.4) |
|
62 |
26×36 (660.4×914.4) |
64 |
28×36 (660.4×914.4) |
|
70 |
30×40 (762×1016) |
72 |
32×40 (812.8×1016) |
|
74 |
34×40 (863.6×1016) |
76 |
32×44 (812.8×1117.6) |
|
78 |
34×44 (863.6×1117.6) |
80 |
36×44 (914.4×1117.6) |
|
82 |
36×46 (914.4×1168.4) |
84 |
36×48 (914.4×1219.2) |
|
86 |
36×50 (914.4×1270) |
88 |
36×52 (914.4×1320.8) |
|
90 |
40×50 (1016×1270) |
92 |
42×50 (1066.8×1270) |
|
94 |
44×50 (1117.6×1270) |
96 |
44×52 (1117.6×1320.8) |
|
98 |
40×58 (1016×1473.2) |
100 |
40×60 (1016×1524) |
上記表の○印が一般的にレギュラーサイズとして使用されている。
アメリカの場合、一般習作用キャンバス枠は2インチ刻みの寸法2本一組で売られており、画家は自由に組み合わせを選択できるシステムとなっている。このため、額縁の販売は日本のように既成額中心ではなく、モールディングシステムの自由なサイズの額縁製作が発達している。
日本における油絵のキャンバス木枠寸法は、フランスの寸法を基本としています。
明治年間にフランス規格を参考にセンチ(cm)を尺寸法に換算して、端数を四捨五入し旧規格が作られました。 しかし、昭和33年の尺貫法廃止に伴い、一尺を303ミリとして換算し端数を四捨五入して現在の規格寸法となっています。(一部に例外があります)
日本のキャンバス寸法表(単位:mm)
|
号数 |
Fサイズ Figure/人物型 |
Pサイズ Paysage/風景型 |
Mサイズ Marine/海景型 |
Sサイズ Square/正方形 |
|---|---|---|---|---|
|
0 |
179×139 |
179×118 |
179×100 |
179×179 |
|
SM |
227×158 |
– |
– |
227×227 |
|
3 |
273×220 |
273×190 |
273×161 |
273×273 |
|
4 |
333×242 |
333×220 |
333×191 |
333×333 |
|
6 |
409×318 |
409×273 |
409×243 |
409×409 |
|
8 |
455×379 |
455×333 |
455×273 |
455×455 |
|
10 |
530×455 |
530×409 |
530×333 |
530×530 |
|
12 |
606×500 |
606×455 |
606×409 |
606×606 |
|
15 |
651×530 |
651×500 |
651×455 |
651×651 |
|
20 |
727×606 |
727×530 |
727×500 |
727×727 |
|
30 |
909×727 |
909×651 |
909×606 |
909×909 |
|
40 |
1000×803 |
1000×727 |
1000×651 |
1000×1000 |
|
50 |
1167×909 |
1167×803 |
1167×727 |
1167×1167 |
|
60 |
1303×970 |
1303×894 |
1303×803 |
1303×1303 |
|
80 |
1455×1121 |
1455×970 |
1455×894 |
1455×1455 |
|
100 |
1621×1303 |
1621×1121 |
1621×970 |
1621×1621 |
|
120 |
1939×1303 |
1939×1121 |
1939×970 |
1939×1939 |
洋紙寸法(OA寸法)というとA3とかB4という寸法を思い浮かべますが、これは昭和初期に日本工業規格(JIS)で決められた寸法です。A列とB列があり、A列の0番は面積1平方メートル、B列0番は1.5平方メートルとして、 また、幅と長さの比はA列、B列ともに、1:1.414(√2)として寸法が決められました。
幅と長さをこの比率にしておくと、長辺を半分に裁断したときも再び短辺と長辺の比が同じになることから考えだされたものです。 また、洋紙にはこのJIS規格以外に絵画や製図などに使われる紙もあり、そのサイズはそれぞれのメーカーの製紙寸法に基づきます。
JIS規格寸法表(単位:mm)
|
名称 |
サイズ詳細 |
名称 |
サイズ詳細 |
|---|---|---|---|
|
B0 |
728×1,030 |
A0 |
594×841 |
|
B2 |
515×728 |
A2 |
420×594 |
|
B3 |
364×515 |
A3 |
297×420 |
|
B4 |
257×364 |
A4 |
210×297 |
|
B5 |
182×257 |
A5 |
148×210 |
|
B6 |
128×182 |
A6 |
105×148 |
水彩画やデッサンに使われる紙の寸法です。
1枚物を全紙、全紙を半分にしたものを半切、半切をさらに半分にしたものを四ツ切と呼びます。
デッサン・水彩用紙の寸法表(単位:mm)
|
用紙 |
全紙 |
半切 |
四ツ切 |
|---|---|---|---|
|
ケント紙 |
1,100×790 |
790×550 |
550×395 |
|
ケント紙BB |
1,030×690 |
690×515 |
515×345 |
|
MO紙中判 |
760×560 |
560×380 |
380×280 |
|
アルシュ中判 |
760×560 |
560×380 |
380×280 |
|
ワトソン紙 |
1,091×788 |
788×545 |
545×394 |
|
マーメード紙 |
1,167×803 |
803×583 |
583×401 |
|
木炭紙 |
650×500 |
500×325 |
325×250 |
|
ワトソン(239g)ロール |
1,130×10M |
– |
– |
|
ワトソン(300g)ロール |
1,360×10M |
– |
– |
|
マーメード・ロール |
1,167×10M |
– |
– |
|
モンヴァルキャンソン・ロール |
1,520×10M |
– |
– |
もっとも広範に使われた和紙のサイズは半紙と呼ばれる333×242ミリ(1尺1寸 ×8寸)のものです。
この名称は『手漉きの全紙を半分にしたことから』始まったようですが、江戸時代に各地大名の間で大きさを競い合い、結果さまざまな和紙のサイズが存在することになったようです。 中でも尾張家(美濃)が漉かせた美濃紙が最も大きく、403×282ミリ(1尺3寸×9寸)で、明治以降、広く全国に浸透しました。
また、中国から輸入したといわれる画仙紙も書や大和絵に盛んに用いられ、現在の表装技術の基本寸法となっています。 このような事情から和紙のサイズを一概に述べることは困難ですが、次に代表的な和紙と画仙紙の寸法を記します。
|
サイズ名称 |
mm |
サイズ名称 |
mm |
|
|---|---|---|---|---|
|
局紙D判 |
439×560 |
全 紙 |
697×1,364 |
|
|
局紙E判 |
470×636 |
ヨコ半切 |
697×682 |
|
|
大塞書及征判 |
394×530 |
タテ半切 |
348×1,364 |
|
|
図引用紙 |
545×788 |
タテ半切1/2 |
348×682 |
|
|
半紙判 |
242×333 |
タテ半切1/3 |
348×454 |
|
|
美濃判 |
282×403 |
タテ半切1/4 |
174×682 |
|
|
西の内 |
333×484 |
連 落 |
515×1364 |
|
|
細川紙 |
606×909 |
全懐紙 |
364×494 |
|
|
半懐紙 |
250×360 |
色紙というと、242×273㎜(8寸×9寸・大色紙ともいう)のものを思い浮かべますが、小色紙・182×212㎜(6寸×7寸)や、絵画規格と同様の寸法の色紙も市販されています。 また、短冊も分類上色紙と呼ばれることがあります。
色紙類のサイズ表
|
呼称 |
サイズ(㎜) |
呼称 |
サイズ(㎜) |
|
|---|---|---|---|---|
|
色 紙 (大色紙) |
242×273 |
ワイドサム |
158×454 |
|
|
小色紙 |
182×212 |
F4色紙 |
242×333 |
|
|
寸松庵 (姫色紙) |
121×136 |
F6色紙 |
318×409 |
|
|
倍判色紙 |
273×484 |
F8色紙 |
379×455 |
|
|
短冊並幅 |
61×364 |
F10色紙 |
455×530 |
|
|
短冊広幅 |
76×364 |
写真の印画紙はメーカーにより若干寸法が異なります。また、現像時の白フチの有無により画面サイズも変わります。ここでは、代表的メーカーのサイズを参考に記載させていただいています。
|
呼 称 |
サイズ(㎜) |
|---|---|
|
全 倍 |
600×900 |
|
全 紙 |
457×560 |
|
半 切 |
356×431 |
|
ワイド四ツ切 |
253×364 |
|
四ツ切 |
253×305 |
|
ワイド六ツ切 |
203×305 |
|
六ツ切 |
203×254 |
|
八ツ切 |
155×206 |
|
キャビネ・2L |
127×178 |
|
ポストカード |
97×145 |
|
L 判 |
89×127 |
組縁とは、塗装などの仕上げを済ませた長い竿状の材料(モールディング・額縁の半製品)をカットし、 それを組み合わせて作られた額縁のことをいいます。
一般額(デッサン額)、賞状額、写真立て、写真額、ポスターフレームなどが主にこの形式で、製法上の呼び名です。 組縁の対極にあるのが本縁といわれ、枠状に組み上げた後に最終仕上げを施す製法で、油絵額などは主にこの形式で作られます。(廉価な油絵額の一部には組縁形式のものもあります)
組縁における規格寸法構成の要因は、絵画などの基底材(紙)の切断寸法や、組縁に使われるガラスの採り分がその基本となっています。
また特に日本の場合、組縁の普及・発展段階でもっとも大きな需要が鏡縁であったため、その寸法が基準となりました。 それらの名残が額縁業界独特のサイズ呼称となって現在も使われています。
いずれにしても、これらのサイズは幾種類もの多岐にわたり、レギュラーサイズとするには複雑すぎて業界としてのリスクが大きいだけでなく、消費者にも理解されにくい問題です。
業界として徐々に単純化・標準化されつつあるものの、まだ完全ではなく、メーカー、販売店によって同じ呼称でも差異があることがあり注意が必要です。
このページはうんちく中心の読み物の側面が強い内容です。
額縁の規格サイズをお調べの方は、ここをクリックして一覧表をご覧ください。